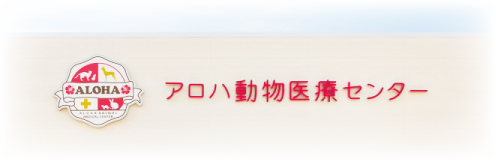🐾【嚥下障害と逆流のやさしい解説】🐾
✅ 正常な「飲み込み」のしくみ
犬や猫がごはんを食べるとき、次のような流れで食べ物が胃に送られます:
舌の動きで口の奥に食べ物が集められる
のど(咽頭)の筋肉が動いて、食道に押し込まれる
食道の筋肉が波のように動いて、胃まで運ばれる
この一連の動きには、顔や舌を動かす神経、のどの神経、食道の神経が正しく働く必要があります。
猫は特に、食道の下の方に「平滑筋」という筋肉があるため、その筋肉も正しく働くことが重要です。
⚠️ 嚥下障害(うまく飲み込めない)
飲み込む動きのどこかに問題がある状態を「嚥下障害」と言います。主な種類は以下の3つです:
口の問題
ごはんをうまくつかめない、こぼす、ずっと噛んでいるなど。
のどの問題
何度も飲み込もうとして吐きそうになったり、食べ物を戻したりする。
食道の問題
食べ物がうまく通らず、逆流や肺に入ってしまうことがある。
※どの部分が原因なのか見分けるのは難しいため、実際の様子を観察したり、動画で確認することがとても役立ちます。
💡 嚥下障害の原因(例)
口の中やのどの炎症(感染・免疫の病気・毒物など)
異物や腫瘍などによる通り道の邪魔
あごの関節の脱臼や骨折
神経や筋肉の病気(筋肉の力が弱くなるなど)
ホルモンの病気(甲状腺の働きが低下する病気など)
🩺 診断と対応
嚥下障害があると、肺炎を起こす危険性もあるため、以下のような診察や検査が行われます:
実際に食べている様子を観察
X線や内視鏡などの画像検査
血液検査やホルモンの検査
神経や筋肉のチェック など
🐶 日常で気をつけること
食事中に変なしぐさがないか注意する
口からこぼしたり、飲み込めていない様子があればすぐ受診
症状が動画で撮れるなら、獣医さんに見せるのがとても有効!